第2回 淡水ガメ情報交換会
終了しました
第2回
淡水ガメ情報交換会
2014年
12月20日(土)・21日(日)
東邦大学
習志野キャンパス
(千葉県船橋市)

参加および発表資格
- 淡水ガメの調査や研究をされている方
- 水辺の生き物や自然に興味・関心がある方
参加費(2日間共通)
- 一般 3,000円 講演要旨集付き
- 学生 1,500円 講演要旨集付き
☆当日参加は500円追加
懇親会
- 懇親会 @学生食堂 2階ホール
一般:4,000円、学生:2,500円、高校生以下:1,000円
当日の様子
第2回目となる今大会の参加者は、116名。
大会初日のシンポジウム「ここまで進んだ! 民官学✕アカミミガメ問題 現状と対応」は、アカミミガメに関する各地の取り組みや研究成果をさまざまな主体が持ち寄って発表する公募型シンポジウムでした。予想外に多くの応募があり、アカミミガメ問題への関心や課題解決の意志が着実に広がっていることを再認識しました。
そのほか多くの発表において、淡水ガメに関する研究や実践が着実に進行、拡大している状況が見えました。
開催準備は主催者が行いましたが、運営上のいくつかの部分では参加者に協力をお願いしました。計22件の寄付と差し入れもいただきました。ご支援、本当にありがとうございます。


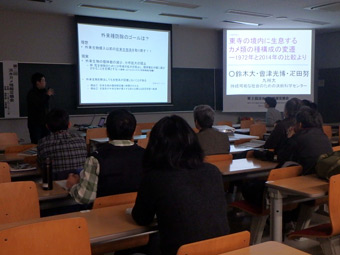
プログラム
12月20日(土)
| 13:00〜17:25 | シンポジウム 「ここまで進んだ! 民官学✕アカミミガメ問題 現状と対応」 コーディネーター:亀崎直樹(岡山理科大学 教授/須磨海浜水族園) |
第1部 ~現状~
- アカミミガメの南西諸島侵攻
嶋津信彦(沖縄生物学会) - 西日本におけるアカミミガメの分布
谷口真理(神戸市立 須磨海浜水族園/香川大学 工学部) - ミシシッピアカミミガメの影響と対策
~彦根城中堀に自生するオニバス群落の保全に向けて~
曽我部共生(京都大学 大学院 農学研究科) - ミドリガメの販売中止を求める活動及び販売状況アンケート報告
東さちこ(PEACE)
第2部 ~研究~
- カメの爪切り −水田生態系に生息するカメ類の生物化学的分析−
森淳(独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所) - ミシシッピアカミミガメによる餌をめぐる積極的干渉
保科明俊(滋賀県立大学 大学院 環境科学研究科) - アカミミガメの繁殖に関する研究
大家巧己・小西翔(栃木県立 佐野高等学校 科学部カメ班)
第3部 〜対応〜
- 素人集団によるアカミミガメ捕獲への道のり
清水淳(北川かっぱの会) - ため池を守り、活かし、継承する「いなみ野ため池ミュージアム」
~地域主体によるため池の生態系保全活動のススメ~
松原隆之(兵庫県 東播磨県民局 地域振興室) - アカミミガメの規制に向けた国の検討状況と市民からの提言
片岡友美(認定NPO法人 生態工房) - 明石市谷八木川におけるアカミミガメ防除
堀貴明(東海大学 海洋学部) - 篠山城の南堀におけるミシシッピアカミミガメの駆除と成果
片岡智美(東海大学 海洋学部) - 徳島県の鳴門市におけるレンコンのアカミミガメによる被害対策
佐藤章裕(徳島県 鳴門藍住農業支援センター)
| 16:40〜17:25 | 総合討論 |
| 18:00〜20:00 | 懇親会 @学生食堂 2階ホール |
12月21日(日)
| 9:30〜11:00 | 口頭発表 |
- 西日本のため池で採取したミシシッピアカミミガメとクサガメの食性
三根佳奈子(神戸市立 須磨海浜水族園) - 岡山県白壁地区のカメ相
友近沙織(岡山理科大学 生物地球学部) - 東寺の境内に生息するカメ類の種構成の変遷 ー1972年と2014年の比較より
鈴木大(九州大学 持続可能な社会のための決断科学センター) - 爬虫両生類情報交換会「南房総イシガメ観察会」による館山市A地区のカメ類の生息状況
~近年のイシガメ減少の原因について~
西堀智子(爬虫両生類情報交換会/千葉県ニホンイシガメ保護対策協議会) - 岐阜市のニホンイシガメを守る生息域外保全の取組み
楠田哲士(岐阜大学 応用生物科学部 動物繁殖学研究室) - ニホンイシガメの起源と化石記録
平山廉(早稲田大学 国際教養学部)
| 11:15〜12:30 | ポスター発表 |
- 年輪を用いた過去サイズ推定方法の妥当性の検証
下藤章(東邦大学 理学部 地理生態学研究室) - mCTを用いたニホンイシガメとクサガメ及びその雑種の頭骨形態の比較
上野真太郎(東京大学 大学院 農学研究科) - 地域で取り組むアカミミガメ防除
~いなみ野ため池ミュージアム運営協議会とともに~
西堀智子(和亀保護の会) - 市民参加でつくる東京のカメ分布図~東京のカメしらべ~(予報)
増永望美(認定NPO法人 生態工房) - 目視調査でカメ類の生息状況を把握できるか?
片岡友美(認定NPO法人 生態工房) - 岡山市笹ヶ瀬川におけるミシシッピアカミミガメ幼体の確認
竹崎千尋(岡山理科大学 生物地球学部) - 2014年カメモニター調査結果とイシガメ訪問の話題
菊水研二(元岡「市民の手による生物調査」) - 千葉県印旛沼水系におけるカミツキガメ防除の現状と課題
秋田耕佑(一般財団法人 自然環境研究センター) - 野生化した外来カメ類の成長速度
小林頼太(東京環境工科専門学校/新潟大学 朱鷺・自然再生学研究センター)
| 13:30〜17:00 | シンポジウム 「房総発、未来へ残そうニホンイシガメの里 ~生息域保全の重要性を考える~」 コーディネーター:長谷川雅美(東邦大学 理学部 地理生態学研究室) |
第1部 ~房総のニホンイシガメは今~
- 房総半島におけるニホンイシガメの危機(Ⅱ)
小賀野大一(千葉県野生生物研究会 ) - 千葉県南房総におけるアライグマによる在来生物への影響と、今後の対策
山﨑響子(東邦大学 理学部 地理生態学研究室) - 千葉県ニホンイシガメ保護対策協議会の設立と活動紹介
近藤めぐみ(NPO法人 カメネットワークジャパン)
第2部 ~房総から全国へ。ニホンイシガメの里を守るために~
- 淡水生カメ類の分布予測と種間相互作用の検討
加賀山翔一(東邦大学 理学部 地理生態学研究室) - ニホンイシガメの保全に向けた生息状況評価の取り組み
髙橋洋生(東邦大学 訪問研究員/一般財団法人 自然環境研究センター)
ブース出展団体
- 公益財団法人 日本自然保護協会
- 株式会社 自然回復
- 認定NPO法人 生態工房
主催・協力
- 認定NPO法人 生態工房
- 神戸市立 須磨海浜水族園
- 東邦大学 理学部 地理生態学研究室
- 千葉県ニホンイシガメ保護対策協議会(協力)
